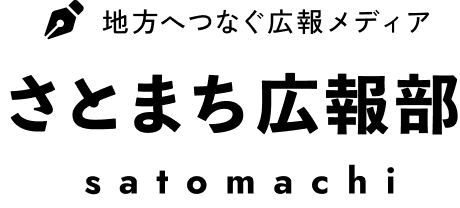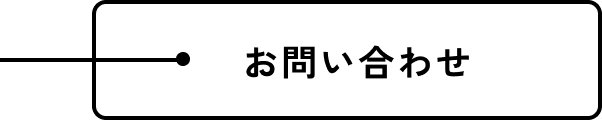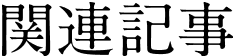2025年9月5日
新潟県佐渡市 真野鶴5代目蔵元、尾畑酒造専務取締役尾畑留美子さん
「自然と文化が育む佐渡の宝物」

世界文化遺産の金山を誇る佐渡島は、自然の宝庫でもある。象徴するのは国仲平野の電柱1本ない田んぼや山々に広がる美しい棚田の景色。佐渡が取り組む減農薬・減化学肥料の米作りはトキの復活を支える。純粋なコメと山の豊かな水は上質の日本酒を産む。130年以上続く「尾畑酒造」の5代目蔵元を務める尾畑留美子さん。人とコメ、水、佐渡の調和で生まれた日本酒を国内外で販売し、廃校になった小学校を酒造りや学び、資源循環を実践する場として再生した。留美子さんの軌跡と試みについて聞いた。
遊び場は日本酒の仕込み蔵
老舗酒蔵の次女として佐渡で生まれ育った。幼い頃に遊んだのは酒の仕込み蔵。薄暗くひんやりした空間に神棚がある。ひとり静かに本を読んだりたたずんだり。「厳かで神聖な雰囲気。心が落ち着く特別な場所でした」。祖父に「私が(酒蔵を)継ぐね」と告げたこともあった。しかし、中学生のとき、5歳年上の姉が義兄と会社を継ぐことが決まる。留美子さんは、「高校を卒業したら島を出る」と人生の方針を変えた。島の外の広い世界への憧れもあった。幼いころから、世界各地を紹介する旅番組をわくわくしながら見ていた。
勉強に打ち込み、東京都の慶應義塾大学法学部に進学。東京は何でもある大都会だった。お気に入りの場所は映画館。実は佐渡島にはなかった。情報誌をめくり興味のある作品を探して映画館に足を運んだ。
サークルは日本酒研究会に入部。他大学との交流や利き酒大会への出場が活動の中心だった。利き酒大会では特別賞を受賞。蔵元の娘として面目躍如だった。

映画館のない佐渡と特技の利き酒
4年生の就職活動。特に希望する業種はなかったが、最終的にコンサルティング会社に決め、内定を得た。就活を終えた秋。学生課を訪れたとき、たまたま目に入った映画会社の求人に心が動かされる。洋画の配給会社ヘラルド映画の宣伝部員。「おもしろうそうだ」と履歴書を送った。書類審査を無事通過。面接試験で「佐渡には映画館がない」と伝えると、「え?なかったかな」と役員らがざわざわ。特技と書いた利き酒の話題になると、興味津々で質問が次々と飛んできた。就職活動の面接でもっとも話が弾んだ。数週間後、採用通知が送られてきた。宣伝部員の募集1名に対して900人の応募者がいたと後で知る。勝因は映画館のない佐渡と利き酒のおかげだったと今も確信している。
挑戦を促す社風で鍛えられる
宣伝部の仕事は、配給する映画のプロモーション戦略の立案、宣伝コピーや宣材の制作、メディアの取材調整など多岐にわたる。「失敗はやる気のある証」と挑戦を促す社風。20代半ばで「氷の微笑」や「レオン」など話題作を任された。思い出深いのは邦画で唯一、担当した橋口亮輔監督の「二十歳の微熱」。新宿の劇場での単館上映で予算も少ない。監督や俳優らと飲み屋をまわってポスターやチラシを配った。「やりたいと思ったことをやらせてもらえました」。
インターネットのない時代。テレビや新聞、雑誌などメディアとの関係づくりも宣伝プロデューサーの重要な仕事だった。懇親会では日本酒をすすめ、飲み交わす。時には明け方まで宴が続いた。そんな中で、大手出版社の編集者だった平島健さんと出会う。健さんの母方の家が造り酒屋。小学生時代の夏休みは蔵で過ごした。境遇の似た二人は意気投合。のちに結婚する。
順調にキャリアを築いていた留美子さんに転機が訪れたのは28歳のとき。きっかけは父の入院だった。生命にかかわる病ではなかったものの、病床で横たわる父の姿を目にして「死」について考えさせられた。もし明日、世界が終わるのであれば、自分は最後に何をしたい……。思い浮かんだのは子供の頃に過ごした仕込み蔵だった。「あの蔵で自分の蔵の酒を飲みたい」。後を継ぐ予定だった姉夫婦は父との折り合いが悪く、家から出ていた。誰に言われるまでもなく「私が継ぎます」と宣言。健さんも「ムコ」として佐渡に行くことを決意し、「一緒に新しい冒険を始めよう」と意気込んだ。
【写真】は映画「二十歳の微熱」打ち上げ後の1枚。留美子さんと橋口亮輔監督(右)、上司の坂上直行部長(左)

人のせいにせず「自分を変える」
尾畑酒造に入社したのは1995年春。消費の多様化で全国の日本酒販売は1973年を境に売り上げ低下が続いていた。業績不振と後継者不在で廃業する蔵は後を絶たない。佐渡島は人口減少が止まらず、主要産業だった観光業も衰退していた。「売上を伸ばす!」「佐渡島を復活させる!」。東京で培ったキャリアと「根拠なき自信」に背中を押され意気揚々と働き始めた。だが、現実は厳しかった。
新しい商品やボトルのデザインを提案しても否定される。業者に相談しても、なかなか返事が来ない。仕事の進め方も時間の感覚も東京とまったく違った。やっとの思いで新しい商品を出しても、思ったように売上は伸びない。やる気が空回りしていた。
行き詰まる状況で、ふと思い出すのは会社を退職する時、上司にかけられた言葉だった。「いつでも戻って来ていいよ。5年は待てるから」。本当かどうかはわからない。それでも心が揺れた。
一方、夫の健さんも試練の連続だった。島の外から来た人は「旅んもん」と呼ばれ、よそ者扱い。「味方は妻だけ」の状態だった。
東京に戻るリミットの5年が迫ったある日、留美子さんは「東京に帰ろうよ」と健さんに問いかける。戻ってきたのは意外な言葉だった。「今、帰ったら負け犬になる」。健さんは佐渡に留まる決意をしていた。自分よりつらい立場の健さんの心中を知って、留美子さんは腹をくくる。不思議なことに退路を断つと、自分の進むべき道が見え、地に足をつけて仕事に取り組めるようになった。新潟県内はもちろん、首都圏での取引が増え始め、国際線の飛行機のファーストクラスの機内酒に真野鶴が採用された。
佐渡に戻って5年。留美子さんは「人のせいにして何も変えられなかった。でも、まだ変えられるものがあった。それは自分自身」と学んだ。

日本酒の海外輸出に挑戦する
留美子さんは蔵の看板商品「真野鶴」を海外で販売する夢があった。映画会社時代、アメリカ出張で利用したレストランのメニューには大手メーカーの日本酒の名前が並んでいた。「いつか真野鶴もメニューに載せたい」。そう思った。
海外輸出の試みを始めたのは2003年。輸出は商社に依頼するのが手っ取り早い。だが、小さな蔵元の依頼は簡単には受けてもらえない。留美子さんは、自分自身で販売ルートの開拓を始める。海外向けに英語のホームページを開設し、情報を発信。販売を請け負う代理店を探した。
真野鶴の海外取引先第一号は、日本酒販売の代理店開業を目指していたアメリカ人の青年だった。送られてきた1本のメールを皮切りに商談が進み、真野鶴初の海外輸出が実現した。その後、この会社との契約は途切れるが、留美子さんはその小さな成功体験を糧に開拓を続ける。日本酒を扱う輸入代理店などが集まる会合に出席し人脈を構築。その中で、知り合ったソムリエが、「日本酒を探しているワイン業者がある」と紹介してくれたことも。少しずつ海外での売り上げを増やしていく。
「小さな蔵ですから、海外輸出にだけ時間と労力を割くわけにはいきません。けれど、そのうち先方から見つけてもらえるようになりました」。現在はアメリカを中心にカナダ、シンガポール、韓国など20ヶ国と取引があり、海外売上比率は20%あたりで推移している。
【写真】佐渡島を訪問した海外輸入業者の方々と

酒に求めらられる個性とは
2007年、イギリスの日本酒鑑評会で尾畑酒造の大吟醸「真野鶴・万穂」が金賞を受賞した。授賞式に参加した留美子さんは受賞した他の酒蔵の銘柄を味わい、蔵元や外国人らと語り合う中で、商品に何が求められているか見えてきた。「おいしいのは当たり前。スペックがよいだけでは売れない。酒の個性とはその酒を生んだ土地や人のストーリーだ」。ワインの販売ではテロノワール(原料となるワインを育む自然環境や生産者の哲学などの情報)が重要視されるが、それは日本酒も変わらない。
その後、尾畑酒造は酒造りのモットーに「四宝和醸」を掲げるようになる。四宝は日本酒の三大要素のコメ、水、人、そこに加えたのは「佐渡」だった。

トキが復活した佐渡と真野鶴
日本酒の海外輸出が縁で交流の生まれた外国人が佐渡島を訪問するようになった。佐渡の田園風景を眺める彼らが口にするのが、「ピースフル(のどかな)」という言葉。佐渡の環境が気に入り、リピーターになる人も少なくない。佐渡の自然はまさに世界に誇る宝物だ。
今に続くこの風景が生まれたのは江戸時代初期のこと。佐渡を直轄地にした徳川家康が進めた金山の採掘事業がきっかけで「ゴールドラッシュ」が発生。流入する人口を支えるため国仲平野を中心に田んぼの開墾が進み、山々の美しい棚田が生まれた。
また佐渡は同じく江戸時代に航路が開拓された北前船の寄港地に。商業が盛んになり、東西各地の文化が入り混じる豊かな島に発展した。
太平洋戦争後の大量に農薬を使う農業は佐渡の生態系に影響を与える。1990年代には、佐渡で保護されていた国内最後のトキが死んだ。絶滅後、佐渡の人々は中国からトキを迎え、「朱鷺と暮らす郷づくり」を始める。減農薬・減化学肥料のコメづくりを促進するために認証米制度を設け、エサとなる虫やカエルが育つ田んぼを復活させた。2008年、初の自然放鳥がされたトキの数は現在、500羽を超える。島民が一体にならないとできなかった試みだ。
尾畑酒造の酒造りもトキを再生する郷づくりとつながっている。真野鶴の原料となる酒米には地元農家が「朱鷺と暮らす郷づくり認証米制度」に則って生産しているものも使用する。佐渡の人々の熱い思いと行動が、真野鶴ブランドの味わいにつながっている。

日本で一番夕陽がきれいな小学校
2009年、PTAの役員をしていた健さんは廃校が決まった西三川小学校を視察のために訪問した。坂道を上った先にある校舎からは佐渡と日本海の美しい景色が一望できた。「日本で一番夕陽がきれいな小学校」と言われていた。健さんは取り壊される運命にある校舎に「希望を見い出した」という。義父から酒蔵の事業を受け継いだが、自分たちの世代で、蔵の未来につながる新たな試みをしたいと考えていた。そこに出会ったのが、丘の上にたたずむ古い木造の校舎。目には見えないパワーが伝わり心がワクワクした。
何ができるか。酒づくり、学び、人々の交流、自然との共生……。様々なキーワードが浮かんだが、まずは校舎に酒蔵つくろうと考えた。提案を受けた留美子さんは驚く。「ひとつの蔵でも大変なのに二つなんてとても無理」と反対した。健さんは戸惑う留美子さんを西三川小学校へ連れて行く。「学びの丘にある、心をワクワクさせるパワーを感じてほしいと願いました」(健さん)。校舎からの風景を見た留美子さんは「佐渡にこんなきれいな景色を見られる場所があったんだ」と心を奪われると、急に使命感が芽生えた。そしてひとこと放つ。「これはやらねばならぬ」。


廃校舎が酒造りと学びの場に
「学校蔵」がスタートしたのは2014年。仕込み蔵は水道がつながっていた理科室を改装した。真野鶴は冬に仕込みをしていたため、新しい蔵は夏に冬の室内環境をつくり仕込むことで、作業期間の重複を避けた。ただ、本社と場所が離れている学校蔵は、スタート時には日本酒製造の免許が得られず、リキュールとして出荷することに。日本酒づくりが始まったのは、日本初の内閣府日本酒特区に指定された2020年だった。
「学校蔵」は酒造りの学びの場としても活用される。2015年から酒造りを学べる日本酒の体験プログラムをはじめた。1週間に4人のチームを受け入れ、麹造りや三段仕込みと呼ばれる作業を体験できる。午前中を中心に酒造りを学び、酒米の田んぼを訪ねたり、水や地形、文化などを学んだりするという。生徒の割合は4人中3人が外国人。SNSを通した口コミで情報を知り、1年前から問い合わせが入るという。2025年8月までに21か国、180人以上が参加した。

循環型の酒造りを実践
留美子さん夫妻の次に取り組んだテーマは環境だ。学校蔵は、資源やモノを地域で循環させる「サステナブル・ブリュアリー」を目指した。実現には知見や技術のあるパートナーが必要だった。「行政、企業、研究機関の方々とお話できる機会があるたびに私たちの構想と思いを伝えました。粘り強さには自信があります」と留美子さん。そのひとつ東京大学未来ビジョン研究センター(当時は東京大学国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構)が共感し、協働でプロジェクトを進めることが決まった。そして2014年、プールに太陽光パネルを設置。その後、増設した。
2022年には元職員室の壁の一部を窓にして、絶景を楽しめるカフェをオープン。メニューには酒造りの過程で生じた酒粕や麹を使ったカレーやスイーツなどを用意した。
校舎の改装も少しずつ進み、宿泊もできる4つの個室や共有スペースを設け、酒造りの体験プログラム参加者や企業研修に利用している。

「学校蔵の特別授業」が起こす化学反応
開校時には有識者を招いたワークショップ形式の「特別授業」も実施され、その後、学校蔵の恒例行事になっていった。地方創生の第一人者で日本総合研究所上席研究員の藻谷浩介さんが「学校蔵のキックオフに行きますよ」と留美子さんに声をかけたのがきっかけだった。二人が知り会ったのは2000年代の前半、佐渡市で開かれた講演会。日本各地の事例や具体的データを駆使した解説に引き込まれ、その後、交流が始まった。「せっかく学校なので、授業スタイルに」と、「佐渡から考える島国ニッポンの未来」をメインテーマにした「学校蔵の特別授業」を企画。第1回は藻谷浩介さん、地方産業の支援企業を経営する酒井譲さんらが講師を務めた。大好評で翌年以降も特別授業は継続。2回目からは佐渡の高校生らも参加。東京の起業家や有名企業の役員、メディア関係者らが世代や社会的立場を超えて、ともに課題について考え語り合った。「参加者の方たちが起こす小さな化学反応がおもしろくて」。特別授業がはじまって11年。これまでに東京大学副学長の玄田有史さん、立命館アジア太平洋大学(APU)前学長の出口治明さん、東京大学名誉教授で解剖学者の養老孟司さんらそうそうたるメンバーが講師を務めている。
【写真】2025年6月の学校蔵特別授業。教壇に立つ日本総合研究所上席研究員の藻谷浩介さんと参加者

長女がムコを連れて後継者に
島民の力でトキを復活させた佐渡島。留美子さんが戻っきた頃の住民は「佐渡には何もない」と自虐的だったが、今は佐渡に誇りを抱いているように思う。美しい自然の中をトキが舞い、佐渡金山は世界遺産に登録された。移住者が営むおしゃれなレストランやゲストハウスも増え、島も変化しつつある。
今年春、東京の大学を卒業し、都内の企業に勤めていた長女がIT企業社員の夫を連れて、佐渡に戻り、二人で尾畑酒造に入社した。学校蔵をはじめ新しい試みを続ける両親の背中を見て決めたらしい。留美子さんは世代交代の時期を意識している。娘夫婦には「あなたたちは自分たちが想像するより早く経営者になるから。今から自分たちが登る山(目標や方向性)を決めなさい」と次の世代の自立を促している。そして留美子さんは佐渡に戻って今年で30年。「日本酒を通して佐渡と世界をつなぐ新しい事業を産み出していけたら」と次の未来を醸しはじめている。

尾畑さんの佐渡島イチオシスポット
大膳神社

佐渡は金山の歴史から能文化が発達し、日本に現存する3分の1の能舞台が残っています。その中でも、尾畑酒造からも近いところにある大膳神社は気持ちが落ち着く場所です。また、佐渡にある30以上の能舞台はそれぞれ雰囲気が違うのも面白いところ。
伝統文化の能が、日常に近いところに存在するのが佐渡島の魅力です。(尾畑留美子)

尾畑留美子(おばた・るみこ)
真野鶴5代目蔵元 尾畑酒造専務取締役
1965年新潟県佐渡市生まれ。慶應義塾大学法学部卒。1988年映画配給会社「ヘラルド映画」入社。宣伝プロデューサーを務め、「氷の微笑」「レオン」などをヒットに導く。1995年尾畑酒造入社。2007年「真野鶴 万穂」がインターナショナル・ワイン・チャレンジ2007大吟醸の部ゴールドメダル受賞。2011年佐渡が日本初の世界農業遺産(GIAHS)に認定される。2014年学校蔵をスタート。第1回「学校蔵特別授業」を開催。2020年学校蔵が日本初の日本酒特区に認定される。同年9月the JAPAN Times SATOYAMA and ESG awards 2020 Satoyama部門大賞受賞。
1965年新潟県佐渡市生まれ。慶應義塾大学法学部卒。1988年映画配給会社「ヘラルド映画」入社。宣伝プロデューサーを務め、「氷の微笑」「レオン」などをヒットに導く。1995年尾畑酒造入社。2007年「真野鶴 万穂」がインターナショナル・ワイン・チャレンジ2007大吟醸の部ゴールドメダル受賞。2011年佐渡が日本初の世界農業遺産(GIAHS)に認定される。2014年学校蔵をスタート。第1回「学校蔵特別授業」を開催。2020年学校蔵が日本初の日本酒特区に認定される。同年9月the JAPAN Times SATOYAMA and ESG awards 2020 Satoyama部門大賞受賞。