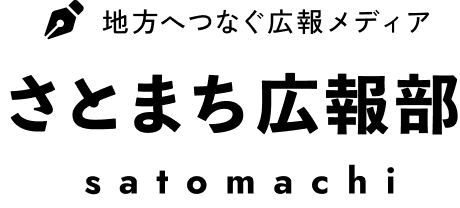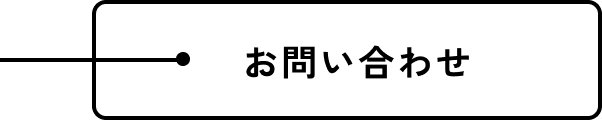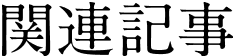2025年7月9日
京都府福知山市「小林ふぁーむ」小林加奈子社長
極上のトマトジュースと里山再生

「小林ふぁーむ」を営む小林加奈子さん(57)は2015年に大阪府堺市から祖母の畑がある京都府福知山市に移住し就農した。作物はトマトとコメの二本柱。老舗の大手デパートでも販売される人気商品のトマトジュースを開発し、コメはサブスク販売で安定した売り上げにつなげている。「就農の道を考える人たちに希望やヒントを届けたい」と語り、農家フランチャイズや農福連携、女性農業者グループの立ち上げにも取り組んだ。小林社長に就農のきっかけや農業の魅力と現実、今後の抱負について聞いた。
塾経営からはじまったキャリア
加奈子さんは大阪府堺市出身。飼っていた犬が大けがを負い手術をしたことがきっかけで獣医に興味を抱き北海道大学に進学した。最終的に選んだ専攻は畜産学科。「家畜動物の誕生から死、消費されることまですべてを学べる」と説明を受け、魅力を感じたという。学部を卒業後は大学院進学を考えていたが、体調を崩し、1年間見送ることになった。この空白期間が進路を変える。実家に戻ると、母親の友人から「かなちゃん、塾せえへんか?」と中学生対象の塾を開くことを勧められ、あっさりとその誘いに乗ってしまう。家庭教師のアルバイト経験のある加奈子さんは、子供に勉強を教えるのが好きだった。畜産を学ぶ中で、「仕事で動物と向き合うのはペットを飼うこととはまったく次元が違う。甘い世界ではない」と知り、将来に迷いもあった。実家のある堺市で個人塾をはじめると、生徒のタイプや実力に合わせたきめの細かい教え方が評判を呼び、1学年15人前後、3学年で50人程度の生徒が毎年入塾した。
ペットのミニブタがきっかけで就農
加奈子さんはミニブタを飼うの夢だった。今から17年前、夫の友人から「岡山県の牧場でミニブタが生まれた」と連絡があり、現地に向かった。出会ったミニブタの赤ちゃんに一目ぼれ。大阪に連れて帰り、「こじろお」と名付ける。むしゃむしゃと野菜を食べる姿がかわいく愛おしい。「もっとおいしい野菜を食べさせてあげたい」と自家栽培を考えた。ふと思い出したのが京都府福知山市にある祖母の畑。耕作をやめて何年も放置された状態だった。それから月に1-2回福知山市に通い、キュウリやトマト、じゃがいもと様々な野菜を農薬や化学肥料を使わずに作り始める。収穫し食べるとスーパーで買う野菜より格段においしかった。
加奈子さんを就農に向かわせたのは、当時の橋下徹大阪府知事が打ち出した高校受験改革だった。学区制が撤廃され、府内の公立高校を自由に受験できるようになった。小さな塾では受験情報の提供には限界があり、生徒にも迷惑をかけてしまうかもしれない。「60歳、70歳になっても塾を続ける自分の姿が想像できなくなりました」。一方で、「田舎で野菜を作りながらこじろおたち動物と楽しく暮らせたら」という理想も抱いていた。年齢も40代半ば。挑戦するなら早いほうがいい。「深く考えずに塾を成功させたように農業もできるのではないか」。ペットグッズや自動車部品の輸入代行業をしていた夫の伸輔さんも就農に賛成した。福知山でつくられる野菜のおいしさを知って、農業に可能性を感じていたからだ。夫妻は2015年、福知山市に移住し、翌年小林ふぁーむを開業。ロゴのモチーフになったのはこじろおだった。


農薬に頼らぬ完熟トマトを生産したが……
翌年から伸輔さんが京都府の制度を利用し、農業研修を受けることになった。指導に就いた女性農業士から、「あんたも教えたるわ」と言われ、一緒に学ぶことに。小林さんは多種類の野菜を育てるつもりだったが、特定の作物に特化したほうが売り込みやすいメリットがあると考えて野菜は大好きなトマトを中心に生産することを決めた。そして、独自の方法でトマトの価値を高めようとする。農薬や化学肥料にはできだけ頼らない。次に完熟にこだわった。一般的な農家の完熟トマトよりもさらに数日待って収穫する。木の上で「もうこれでもか!」というくらい真っ赤になるまで待つ。指導役の女性農業士からは「もっと早く採りなさい」と怒られたとか。「やっぱり全然味が違います。自分がおいしいと思うものをお客様にお届けしたかった」。ところが、完熟したトマトは柔らかいため宅配便で運ぶと形が崩れてしまった。自分の車でそっと地元の売り先に持っていくしか手段はない。せっかく収穫した完熟トマトはさばききれなかった。

「苦手な人」にもおいしいトマトジュースの誕生
農業担当の京都府職員に相談すると「捨ててしまうくらいならジュースにしてみては」と助言された。加工は隣町の社会福祉法人が営む工場で引き受けてくれるという。早速完熟したトマトを工場に持ち込んだが、外せないリクエストがあった。実は、加奈子さんはトマトジュースが大の苦手。「加工臭がどうにも我慢できなくて」と飲めなかった。「私でも飲めるレシピを考えてほしい」と依頼した。その結果、180mlのジュースに6個のトマトを使用し、水も塩も使わない完全無添加の濃厚なジュースが完成した。
試作品を飲んだ伸輔さんらは「おいしい!」と口をそろえて絶賛。それでも加奈子さんは苦手意識を克服できず試飲するのをためらった。秋になって「生産者としての責任がある」とついに飲んだ。そして驚いた。「あのイヤな香りがまったくしない!」。感動と同時に「私と同じタイプの人に喜ばれるかもしれない」と本格的な商品化に心が傾いた。
記録的豪雨災害の逆境を乗り越える
2018年春、伸輔さんが2年間の農業研修を修了。トマトジュースを本格的に販売するために小林ふぁーむを法人化した。
ところが、その年の夏、西日本を記録的な豪雨災害が襲った。折しもトマトの収穫最盛期。小林ふぁーむのビニールハウスは浸水しトマトは泥にまみれた。突然の天災に「どうしようもない」とあきらめかけていた小林さん。そこへ近隣に住む女性の友人2人がかけつけ、「この中に被害に遭わなかったトマトがあるはずや。1個でも2個でもいいから収穫しよう」と励まされた。3人でドロドロになりながらトマトを収穫。ひとつひとつきれいに洗い流した。加工先である社会福祉法人の職員にトマトを見せると、「傷もできていないし、十分トマトジュースにできますよ」と言ってくれた。水害前に収穫できたものを含め手元にあるトマトを集めて持ち込むと、数百本程度のジュースができたが、販売するには量が少ない。翌年に向けて伸輔さんが試作品を手に営業を始めた。
水害の2か月後の9月から商談会に出るようになり、試飲してもらうと大好評だったという。大手百貨店の高島屋との契約が決まり、翌年2月には東京で開催された大型商談会の新製品コンテストで大賞を受賞した。
販売契約は順調に伸びていく。理由には商品力はもちろん、伸輔さんの交渉手腕もあった。「元バイヤーなので、バイヤーが何を知りたいか雰囲気でわかるそうです」。価格、原材料のトマトのクオリティー、ジュースの味、農福連携……。「相手の知りたい情報をその場でつかみながら、いろいろな角度から商品をアピールすることで成約に結びつけています」。

農家フランチャイズで生産拠点拡大
水害の影響でその年のトマトの仕事は夏の半ばで終了。少し時間的余裕ができると、知人から「ビジネスコンテストに参加しないか」と声をかけられた。ファームが被害を受け「これからの農業のかたちをどうするか」と模索していた加奈子さんは参加を決める。
コンテストはビジネスについて学ぶ機会になった。審査員から「生産農場が1か所だけだと災害で全滅するリスクがあります。被害が出たから今年のジュースは出荷できませんと言うような取引先とは誰も契約してくれませんよ」と指摘を受ける。生産拠点を増やしリスクを分散させる必要性を感じた小林さんは、「農家フランチャイズ」の仕組みを導入した。契約農家にトマトの苗と肥料、栽培のノウハウを無償で提供し、収穫したトマトはすべて買い取るというモデルだ。募集すると既存の農家からだけでなく、就農に関心のある会社員からも応募があった。「フランチャイズを3年間経験した会社員の男性はトマトを育てながら農業の仕組みや取引先の開拓を学び、メロンやイチゴをつくる兼業農家になりました」。フランチャイズの取り組みはこのように農業の活性化にも役立っている。

住民らが力を合わせて里山再生
小林ふぁーむのトマトに次ぐ生産の柱はコメだ。2015年福知山市で就農した時、土地は祖母がもつ小さな田んぼでコメをつくりはじめた。その田植え姿を目にした周辺の農家から「うちの田んぼもやってくれへんか」と声がかかり、無償で田んぼを貸してくれるようになった。周辺には田植えをやめた休耕地がたくさんあり、藪になっている場所もあった。
日本全国で農業人口は減少傾向にある。高齢化が進み、新たな就農者は少ない。小林さんが暮らす福知山市の六十内(むそち)集落も例外ではなかった。
小林さん夫妻が積極的に田植えを引き受けたことは、集落の再生につながっていく。地元農家との付き合いが生まれた伸輔さんは、「休耕地を棚田に戻し、元の里山にしましょう」と呼びかけ、2018年「六十内をきれいにする会」を立ち上げる。集落の人々の思いは一緒だった。それまでは休耕地の草むしりや管理を各農家が単独でしていたが、担い手の多くは高齢者。作業が追いつかず、やむなく土地は荒れていった。「一人でなくみんなでやるという言葉が農家の方たちの心に響き、お互いを刺激し合いながら活動を進めました」と加奈子さん。集落の人々が空いている時間を使い、草を刈り、壊れている水路を修復し、獣害対策用のフェンスを張った。休耕地は田んぼへよみがえり、そして翌年からはヒマワリ栽培も開始。その畑の広さは数年で20アール、本数は1万5千本以上に。見ごろのシーズンには毎年、市外から多数の見物客が訪れるようになった。これらの作業にかかる経費は、伸輔さんが補助金制度を調べ申請することで参加者の負担を軽減したという。

加工工場で働く若者の自信につながる
小林ふぁーむは農福連携でも大きな役割を果たしている。トマトジュースの生産を始めた頃は、加工する社会福祉法人の職員から「トマトをどんどん持ち込んでください。それがここで働く人たちの給料に、やりがいにもなるんです」と強く求められた。トマトジュースが表彰されたりメディアで紹介されたりすると加工場も注目を受けるようになり小林ふぁーむ以外からの依頼が急増。今では仕方なく注文を断るときもあるという。「商品が認められたことは、施設で働く若い人たちの自信につながりましたし、そのご家族の方にも喜んでもらえました」。
女性農業者グループの結成
2020年、小林さんが発起人となり女性農業者のグループ「のら×たん ゆらジェンヌ」を結成した。名前には野良(田畑)の仕事を楽しみながら丹精を込めて作物をつくる由良川沿いに住む農業女子の意味を込めた。「昭和の農業は男の人の仕事で、平成になって農業女子をいう言葉が生まれ、令和になってジェンダー平等が叫ばれ、男女が関係なく働く環境になってきていますが、地方の農業は今でも昭和からあまり変わらず前に出ている女性は少ない」。小林さんがグループを立ち上げたのは、女性農業者が連携することで、前に踏み出していく機会になればという思いからだった。
「移住したばかりの頃は、ひとりで畑仕事をしていて小さな愚痴をこぼしたり、情報交換したりする相手がいませんでした。農家の女性と知り合うと、技術や知識があって、おいしい野菜をつくっている人がたくさんいました。そんな女性らがつながり交流ができたらと声をかけました」
現在は、30代ー~40代を中心に10人~20人程度のメンバーが在籍している。小林さん自身は「若い人たちの主体性を促すために身を引きたい」と今春卒業したが、今もメンバーを応援し続けている。

自分で価格を決められる農家を目指す
小林さんは今後の抱負について「若い人たちが将来目指す職業のひとつとして農業を選んでもらえるようにしたい」と語る。先述の通り、農業人口は減少傾向にある。その大きな理由が厳しい仕事の割に収入が得られないことだ。
「稼げる農家になる必要があります。私たちは自分で価格が決められる農業を実践しています」。たとえば人気のトマトジュースは、コストが高いので、一番小さいサイズの180mlでも千円以上の価格だが、それでも注文は入る。コメもJAに決められた価格で卸すのではなく、SNSや口コミで顧客を開拓しサブスクで販売することで安定した売れ行きを確保している。
最近は農業に関心を持つ若い世代から「小林さんの農業は戦略的でビジネスとしての可能性を感じる」と言われることもあるという。小林さんは「農業の枠を広げて、ビジネスとしてとらえるきっかけにしてもらいたいと思っています」と語る。

商品に関するお問い合わせ
株式会社小林ふぁーむ
住所 〒620-0000
京都府福知山市字上小田175
電話・FAX 0773-21-5810
メール info@cobafarm.com
オンラインショップ https://cobafarm.net/

小林加奈子(こばやし・かなこ)
小林ふぁーむ代表取締役。1967年生まれ。大阪府堺市出身。北海道大学農学部畜産学科卒。大学卒業後、25年間学習塾経営。2016年京都福知山市に移住し「小林ふぁーむ」を開業。2018年法人化。2019年農家フランチャイズスタート。2019年京都女性起業家賞(アントレプレナー賞)にて近畿経済局長賞受賞。2020年京都府から女性初の指導農業士認定。女性農業者グループ「のら×たん ゆらジェンヌ」結成
小林ふぁーむ代表取締役。1967年生まれ。大阪府堺市出身。北海道大学農学部畜産学科卒。大学卒業後、25年間学習塾経営。2016年京都福知山市に移住し「小林ふぁーむ」を開業。2018年法人化。2019年農家フランチャイズスタート。2019年京都女性起業家賞(アントレプレナー賞)にて近畿経済局長賞受賞。2020年京都府から女性初の指導農業士認定。女性農業者グループ「のら×たん ゆらジェンヌ」結成