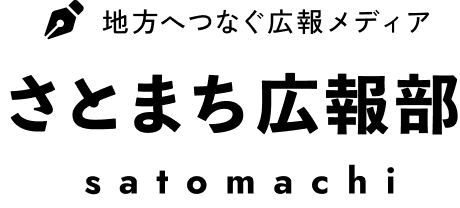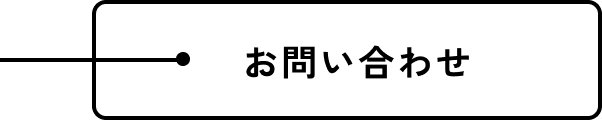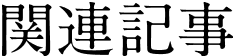2025年10月30日
富山県射水市 水産加工会社IMATO東海勝久代表取締役 漁師の新たな可能性を拓く

多種で豊富な魚介類が生息し「天然の生け簀」と言われる富山湾。その沿岸にある射水市新湊は富山県内でもトップクラスの漁獲量を誇る。新湊内川エリアの漁師、東海勝久さんはフリーターからプロの漁師になり、その後水産会社を興す。価格の安かったカレイのブランド化や世界に類のないカニの干物の開発に成功。漁業の新しい価値を築いた。漁船の観光利用や海洋深層水を使った塩の生産も手掛ける。だが、ここに至るまでは苦難の連続だった。漁師になって30年。その軌跡について聞きました。
フリーターから漁師に転身
東海さんは、中学生の頃から「将来は何かの商売で身を立てたい」と志していた。祖父母が兼業農家。コメを生産し、決められた時期に対価の金銭を受け取り、経費を精算する商売の仕組みが「面白い」と思ったからだ。
学校卒業後は、アルバイトをしながら自分に適した仕事を探した。配管工、飲み屋、スーパーのレジ打ち、建設現場の鳶職……。様々な仕事を経験した。20歳のとき、地元の後輩がハローワークで漁師の募集を見つけ、「網元の面接に付き添って欲しい」と頼まれ同行。面接の結果、後輩は無事、採用されたが、同時に網元から「あんたも一緒に働かないか」と声をかけられた。アルバイトで漁師の経験があった東海さんは、興味もあったので就職を決めた。しかし、同僚の漁師と漁の手法で方向性が合わず3年ほどで退職。ほかの漁師に「辞めたなら、うちに来ないか」と声をかけられて大型の定置網漁をする網元に転職した。

漁師として独立を果たす
漁業組合の矢野恒信組合長は「若い者をどんどん登用して経験を積ませたい」という方針だった。その頃、漁業の世界で生きていくと決心していた東海さんは組合長に「独立させて欲しい」と訴えた。独立するには組合に漁業権を認められる必要があった。矢野組合長からは「おまえはどんな漁業で生計を立てるつもりなのか、ビジネスモデルを書いた計画書をもってこい」と宿題を出された。それからビジネスモデルを考え始める。免許が発行されたのは2年後だった。「大した内容は書けませんでしたが、組合長の温情や期待のおかげで認められたと思います」。
ベテラン漁師に受けた屈辱から一念発起
独立は試練の始まりだった。その頃は漁業のノウハウを十分には理解できていなかった。網元に勤めていた頃の漁法は、魚の通り道に大きな網を仕掛け、魚を誘導して捕獲する定置網だった。安定して魚を獲れるが、設置するには資金がかかる。そのため独立したばかりの東海さんは刺し網漁(※)を始める。だが、まったく魚が獲れなかった。広い海で魚のいる場所が把握できなかったからだ。
※刺し網漁 魚の通り道に網を垂直に張って、魚が網目に刺さったり、絡まったりしてかかるのを利用して漁獲する方法
まる1日かけてたった50円、100円程度の水揚げしかできない日もあった。「このままでは食べていけない」と悩んだ。そんなある日、魚市場で小さな魚を活魚ケースに入れて並べて買い手を探していると、通りがかったベテラン漁師から「なんじゃこりゃ、わしらこんな魚は捨ててくるもんや。恥ずかしいもん並べるな!」と活魚ケースを蹴飛ばされた。「悔しくて悔しくて。本当に屈辱でした」。ただ、それがきっかけで「今に見てろよ!」という熱い気持ちが湧きあがる。海と魚について徹底的に勉強を始めた。船で寝泊まりし24時間体制で漁に取り組んだ。体が横になれるように業者に頼んで船のエンジンルームを平らにしてもらい寝床をつくり、食事はスナック菓子、バナナ、ソーセージでしのぎ、少しずつ経験を積んでいった。

カレイのブランド化に成功
研究と実践を繰り返すことで、自分の漁場で何が獲れるか把握できるようになった。そのひとつが渡り蟹。魚は漁獲量が増えると、価格が下がるが、渡り蟹は価格が変わらない特徴がある。「そんなに高くは売れませんが、安定した収入源になりました」。
もうひとつはカレイ類。地域によっては1匹1万円で売れる。しかし、新湊の市場では1匹たった50円しか値が付かない。親しい仲買人に聞くと「こっち(新湊)のカレイは泥を吸ってくさいから売れん。だけど傷をつけずに生かしてもってきたら1匹500円で買うよ」と言われた。そこで20匹ほど水揚げして売りに行くと、「そんなにいらんよ」と断られた。
それでも東海さんはあきらめなかった。「カレイを高く売るには、この泥臭さを何とかしないと売れない」。組合が所有していた水槽に入れて、泥を吐かせようと考えた。実際に試みると一晩で泥臭さが消えたという。「後日、テレビの取材で水槽に入れたカレイを定点観察すると、確かに泥を吐き出していました」。
カレイの価値を高めるためにブランド化を思いついた。漁師仲間らは「組合や会社ならともかく、漁師個人で魚をブランド化するなんて聞いたことがない」と言われたが、実行に移した。ブランド名は「万葉かれい®」。奈良時代の歌人で、氷見や新湊にゆかりのある大伴家持が編纂した万葉集の名をヒントにした。
すし店や居酒屋に万葉かれいを持参し、「一度、試してください」と試作品として提供した。「さばくときの泥臭い臭いを感じない」と評判は上々。たまたまその頃、ヒラメから寄生虫が検出された影響もあって、代替品として万葉かれいに特需が起きる。富山県外の料亭からも声がかかり、ピーク時は1匹1万5千円の値が付いた。一過性でなく現在も万葉かれいの人気は続いているという。

子どもや高齢者のためのおいしい干物を開発
「子供のさかな嫌いを治したい」。そう願う若い主婦らのために魚のさばき方や料理方法を教える料理教室を開いていた東海さん。「子供にも食べられる干物をつくってほしい」と相談を受ける。干物はもともとが保存食。日持ちがして簡単に食べられるが、塩分が濃く、しょっぱいので子供は受け付けない。塩分の過剰摂取は高血圧の原因にもなり中高年層の健康にも悪影響を与える。社会的なニーズはある。塩分を抑えたおいしい干物の商品化を引き受けたが、程なく「安請け合いしてしまった」と痛感する。そもそも魚の加工をした経験がない。水分の抜き方を自分なりに実験したが、製法を確立するのは簡単ではなかった。
その後、干物づくりは富山県食品研究所との共同研究となり、協力を得ながら、魚の開き方、塩の振り方、乾燥時間など製法をマニュアル化していった。最終的に旨味のある干物ができるまでに1-2年を要した。
「冗談のような話ですが、干物ができても、言い出しっぺのお母さんたちが全然買いに来ませんでした。子供は成長して大きくなっていました」。そこで、小さな子供のいる母親に「この干物はおいしいから。子供たちに味見をしてほしい」と声をかけてまわった。「うちの子どもは魚を食べんが(食べないよ)」と言われつつも、親子のグループに試食をしてもらうことに。子供らは、最初こそ恐る恐る口にしていたが、その後は我先にと手を伸ばした。「子供たちは魚が嫌いなのではなくて、生臭さが苦手なだけ。新鮮な魚はおいしいと感じる」と確信した。その後、干物は「越のひもの®」と名付けられ販売される。ブリやノドクロ、イカ、ゲンゲなど種類は様々。それぞれ鮮度にこだわり高い品質を確保している。

世界で初めてカニの干物を開発・商品化
東海さんは、魚の干物と同時に世界初のカニの干物の開発に挑み完成させた。ところが、開発した本人がカニアレルギー。先輩の漁師らに、試食してもらうと完成させた。試食してもらうと「こんな味は初めてや。うまい!」と大好評。「特許を取ったほうがいいぞ」と助言も受けた。
とはいえ、特許についての知識はない。世間に存在しないカニの干物をどのようにビジネス展開すればいいか方法もわからなかった。考え込んでいると、商工会議所の職員から「とやま起業未来塾」の受講を勧められた。起業や新規ビジネスの立ち上げを目指す人にマーケティングや財務について指南し、さらに事業計画の策定やブラッシュアップを支援する組織だ。東海さんは入塾を決める。
未来塾では1年目に干蟹の特許出願に取り組んだ。事業はアドバイザーからも評価され、特許出願に向けて動き出す。あるとき事業のプレゼンイベントがあり、干蟹について語ろうとした東海さんは、アドバイザーから止められる。「出願前に不特定多数の人の前で開発について語ると、新規性を失い、特許の要件が満たされなくなる」と説明を受ける。学ぶことは多かった。
2年目は材料の仕入れ先の選定や全国展開するためのコストの算出、ビジネスモデルの構築を成し遂げ、塾を修了した。。
2018年、水産加工会社「IMATO」を設立。特許出願と商標登録を済ませ、満を持して「越の干蟹®」を発売した。日本初のカニの干物は瞬く間に話題になり注文が殺到。富山産だけでは注文をさばき切れず、鳥取の境港からも紅ズワイガニを仕入れることにした。「越の干蟹」は富山県を中心とした地域で、全国展開する商品は、海外産のカニも利用して「かにぼし®」のブランドで販売している。


漁業以外のビジネスにも積極的に挑戦
20代で漁業を始めた東海さんだが、漁師との人間関係に悩まされた時期があったという。挑戦を支えてくれた組合長が退任し、新しい組合長が就任すると、「自分に対するまわりの目は急に厳しくなった」という。漁師の子弟ではない「新参者」で、しかも新湊ではなく隣りの氷見市出身だったために「よそ者」の扱いが露骨になった。何より新しい試みに挑む東海さんは古くからの慣習がある漁師の世界では異端児だった。「大人のイジメと言いますか。もう漁師をやめてしまう寸前まで追い詰められました」。それでも後輩らに励まされて耐え抜いたという。
一方で、「新参者でよそ者だったからこそ、慣習にとらわれず、新しいビジネスに目が向いたように思います」と語る。そのひとつが先に紹介した加工販売だった。漁師の仕事は天候や海の状態で3分の1は海に出られない。加工の仕事があれば、その間、天候に関係なく働くことができて、漁師の収入につながる。「漁師の成り手は減っています。副業は収入の不安定な若手の漁師に安心を与え、その結果、漁業の未来にもつながります」。
東海さんは海上タクシーの免許を取得し、10年ほど前から観光船の事業も始めた。遊休中の漁船を使い、観光客を乗せて内川から海の沿岸をクルーズする。「観光事業は漁の好不調に関わらず漁師の収入確保につながります」。近年は富山県も観光事業に力を注ぎ、内川に遊覧船を走らせている。日中だけでなく湊からの夜景を楽しむ乗船客も増えているという。
今年に入って富山県滑川市沖の海洋深層水を使った「富山の塩」の製造販売も始めた。ほどよい甘味とミネラルのバランスの良さが特徴という。「自分にとっては海そのものが事業資源です。富山の自然をいかした健康にいい塩が名産になれば」と語る。


俳優舘ひろしさんに「船長!」と呼ばれた映画撮影
今年11月に公開される俳優舘ひろしさんが主演する映画「港のひかり」。昔ながらの港町の風景が残る内川は、映画やドラマのロケ地に何度も選ばれている。富山県庁の職員から「スタッフの方々のロケハンに付き合ってほしい」と依頼された東海さんはガイドを引き受ける。山岳映画の巨匠と呼ばれるカメラマン木村大作さんらスタッフを連れて内川を案内していると、信頼されたのか、漁船の提供や漁業指導、さらには撮影中の操船も依頼された。撮影期間は2か月弱。本業にも影響するが、それでも、「内川エリアや富山県の宣伝になるなら」と承諾した。
撮影が行われたのは富山県や石川県能登地方。撮影中はずっと張り付き、船の修繕作業の仕方や漁師の所作、聞かれたことに対して端的に答えた。舘ひろしさんにはいつも「船長!」と呼ばれていたとか。「せっかくなので撮影に使われた第五招福丸は公開後に観光船としても活用したいと思っています」。
近年の内川は古民家を再生したカフェやホテルが開業。漁師町の風情や観光クルーズも注目され、富山県で推される観光地の一つになっている。東海さんは店舗の前に船を寄せて撮影の場面づくりをしたり、宿や飲食店に新鮮な魚を提供したり内川の活性化のための協力は惜しまない。一方で、気がかりもある。内川の知名度が上がるとともに、他地域から進出する事業者も増えている。「ただ、人気があるからという理由で、内川に来て商売するのではなく、まちの長い歴史や伝統、ルールは理解して、地域の環境や人との関係を大切にして欲しいですね」と語る。



東海勝久(とうかい・かつひさ)
水産加工会社IMATO代表取締役
1975年富山県氷見市生まれ。1995年網元に就職。2004年漁業者として独立し東海水産設立。2011年沿岸漁業研究会を立ち上げ「万葉かれいⓇ」を商標登録、ブランド化。2014年、射水市漁業協議会を設立し「越のわたり蟹Ⓡ」を商標登録、ブランド化。2018年株式会社IMATO設立。代表取締役に就任。「越のひものⓇ」「越の干蟹Ⓡ」を発売。2025年「越の干蟹」が富山県推奨とやまブランドに認定される。富山湾の海洋深層水を使った天日塩「富山の塩」の発売開始
1975年富山県氷見市生まれ。1995年網元に就職。2004年漁業者として独立し東海水産設立。2011年沿岸漁業研究会を立ち上げ「万葉かれいⓇ」を商標登録、ブランド化。2014年、射水市漁業協議会を設立し「越のわたり蟹Ⓡ」を商標登録、ブランド化。2018年株式会社IMATO設立。代表取締役に就任。「越のひものⓇ」「越の干蟹Ⓡ」を発売。2025年「越の干蟹」が富山県推奨とやまブランドに認定される。富山湾の海洋深層水を使った天日塩「富山の塩」の発売開始