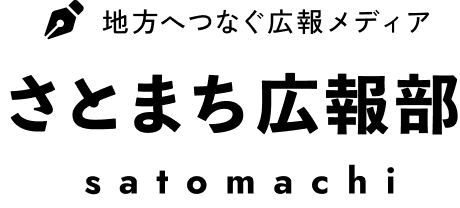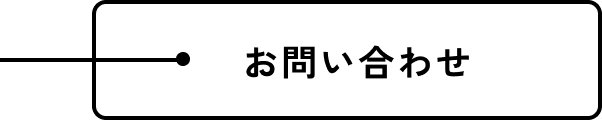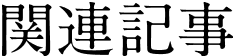2025年3月31日
愛媛県今治市 柑橘農園経営、加工商品企画・販売業 小川竜也さん、幾子さん
京都市から就農移住「おいしいみかんを残したい」
おいしいみかんを後世に残すために京都市から就農移住

柑橘農園経営、加工商品企画・販売業
小川竜也さん(42)、幾子さん(39)
瀬戸内海のしまなみ海道沿いにある愛媛県今治市の伯方島。青い海に浮かぶ島々を見下ろす丘陵地で、柑橘農家を営む小川竜也さん(42)、幾子さん(39)夫妻は京都市から移住して2年になる。その間、5人の子育てをしながら竜也さんは休耕地を切りひらき、幾子さんは介護施設で働きながら加工商品の企画・販売をはじめた。地方暮らしも農業もまったくの未経験だった二人が、過疎化が進む小さな島で奮闘する動機とは。
ママ友のおじいさんが愛媛県の伯方島で柑橘農家をされていて、毎年みかんを京都市の家に送ってもらっていました。それがすごくおいしくて。我が家の冬に欠かせない風物詩でした。ところが、2022年のはじめ、おじいさんが高齢のために柑橘の栽培は今年で最後になるかもしれないと聞かされました。人口が減少する島に後継者はおらず、廃業後は木も伐採してしまうということでした。
このおいしいみかんがもう二度と食べられなくなる。そんな人生は想像できない。そう思うと、いてもたってもいられず、「私が後を継いで、みかんを育てます!」とママ友に申し出てしまいました。とはいえ、話はそう簡単ではありません。
私と夫は神奈川県秦野市出身。夫は工務店や運送業で働いたのち、独立し、京都市で焼肉店を経営。私は介護施設で働きながら店を手伝っていました。
農業にはまったく縁がなく、しかも中学生を筆頭に5人の子どもがいました。もし、柑橘農家を継ぐとしたら、夫が京都に残り家族の生計を立て、私が子供を連れて伯方島で柑橘農家の仕事をすることを想定しました。
ところが、夫に相談すると、意外な返事が戻ってきました。「僕が行くよ。焼肉屋はいつでもできるけど、一度なくなったみかん畑は元には戻せない」。聞くと、夫は就職する前にバイクで沖縄県に旅行した経験があり、「いつか海辺の町で暮らしたい」という夢もあったようです。

瀬戸内海の景色に一目ぼれ
新型コロナウイルスの流行が落ち着いた、その年の5月、夫と三男が二人で伯方島を訪ねました。紹介してもらったママ友のおじいさん、藤原豁博(かつひろ)さんに農園を案内され、そこから見える瀬戸内の青い海に島々が浮かぶ景色を目にした夫は「自分はこの地に呼ばれている気がする」とすっかり島に魅了されました。
8月には一家全員で島を訪問しました。子供たちを海に連れて行くと、すごくうれしそうにはしゃいでいました。私と夫で「ここで柑橘の仕事をしたい」と伝えると、藤原さんは「ホンマに来るんやな。だったら、家を探してあげるよ」と言ってくれました。
11月「家が見つかったよ」と連絡があり、島を再訪しました。夫が単身赴任で私が京都で子供たちと暮らす予定でしたが、できれば家族一緒に島で暮らしたい。そう思った私は島で仕事を探すことにしました。レンタカーで島をまわり、たまたま目に入った介護施設に「職員を募集していませんか」と飛び込み、即採用が決まりました。

百姓は百のことができる人
移住したのは2023年4月です。
夫は「JAおちいまばり」の紹介で認定農家の方から柑橘栽培の研修を受けながら、藤原さんの柑橘農園を手伝い、知識と経験を積んで行きました。
家族が暮らす収入を得るには自分たち自身で農地を借りる必要がありました。
JAに相談すると、「土地の借りることは大変ですよ」と言われましたが、藤原さんの紹介のおかげで、農家の方から休耕している土地を貸してもらえました。放置されていた土地は草や竹が伸びてジャングルのようでしたが、置いてあったユンボを「使っていいよ」と言われたので、救われました。夫は、竹を切り、土を掘り起こして、平らな土地に変えていきました。
工務店で一から学び、厳しい仕事をしながら、自分の技術を磨いていった経験があるので、新しい農業という仕事にも、楽しみながら取り組んでいました。
「百姓は百のことができる人のこと」。藤原さんから教わった言葉を座右の銘に「おれは百姓になる!」と励んでいます。

廃棄みかんを活用するための店舗「OMOYA。」をオープン
藤原さんはみかんを減農薬で育てていました。甘味があっておいしいのですが、かたちが不ぞろいになる傾向があり、捨てられるみかんも少なくはありませんでした。私は加工品にすれば、かたちは関係なく、みかんを味わってもらえると考えて、商品開発をすることにしました。もちろん、経験はまったくないので、京都に住むアイスクリーム職人の友人、隣の島の工房の方たちに協力をお願いして、みかんの実や果汁はアイスクリームやゼリーに、皮はアロマセラピーの精油にしました。味や香りを損なわないように工夫しました。島のお土産や贈り物に選んでもらえるようにパッケージのデザインにもこだわりました。
販売所は家の敷地になる納屋を使いました。島の方からは「母屋(おもや)」と呼ばれていたそうで、それにちなんで屋号は「OMOYA。」にしました。オープンは2024年5月。販売を始めると、島の人だけでなく、インバウンドの外国人の方々にも売れました。

樹になるゼリー「紅まどんな」
夫は指導を受けていたJAの認定農家の方の助言で、温州ミカンのほかに交配品種で樹になるゼリーと呼ばれる「紅まどんな」の栽培を目指しました。人気が高く、値段も高く販売できる。そのためには新たな農地とビニールハウスが必要でした。
購入資金は就農者への補助金で2棟分はまかないましたが、それだけでは足りません。そこで、伯方島や近隣の島を自動車でまわり、使われていなさそうなビニールハウスを探しました。運よく耕作をやめて、ビニールハウスの処理に悩んでいた住民の方を見つけ、無償で譲ってもらうことができました。分解した材料を運び、業者を雇わずに自分でてきぱきと組み立てました。ここでも工務店での経験がいきました。
紅まどんなの苗木は現在300本。最終的には1千本を目指しています。
販売できるのは3年後。労力や経費はかかりますが、そこに賭ける価値は十分あります。
農業は適正な値段で取引ができたら、採れた分だけ収入を得られる仕事です。
今は5か所目の農地の開墾に取り掛かっているところです。獣害の被害もあるのでリスク分散は欠かせません。

絶品の温州みかんを次世代に受け継ぐ
私たちの一番の目標は、藤原さんが育ててきたみかんが次世代に受け継がれて、残されていくことです。県外で働いている藤原さんのお孫さんもいずれ伯方島に戻り、農家を継ぐことを希望しています。自分たちが借りて、耕してきた土地を引き継ぎ、新たに生産者となる人の役に立てたら、「頑張ってよかった」と言えるような気がします。とはいえ、伯方島では農業をやめる人が増えています。私たちはその畑を引き継ぎ、島の柑橘業を持続させるために頑張っていきたいです。