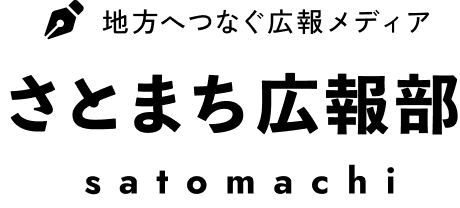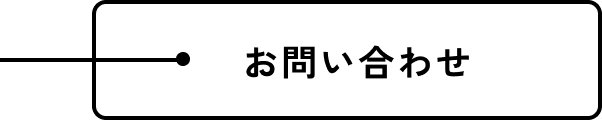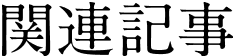2025年3月31日
沖縄県石垣市 花谷農園 花谷まゆさん
子供の未来を守る農業と環境づくり

サンゴ礁の海で知られる石垣島。内陸部には田園地帯が広がり、豊かな野菜が生産されている。東京農業大学出身の花谷まゆさん(43)は、農家の長男との結婚を機に石垣市へ移住。息子のぜんそくアレルギーを治すために有機農業を始めたのをきっかけに、自然環境にも目を向け、減少傾向にあるサンゴ礁を守るローカル認証制度を仲間と立ち上げた。その取り組みと狙いについてうかがった。
結婚を機に石垣島へ
石川県能美市出身です。実家は農家で子供のころから手伝いをしていました。テレビCMで流れる飢餓で苦しむ子供たちの姿を見て、将来は後進国の食糧増産のための活動をしたいと思いました。高校卒業後、東京農業大学国際食糧情報学部に進学し、途上国の主食を研究しました。春夏の休みには東南アジアでバックパッカー旅行をして、貧困地域を実際に自分の目で見て回りました。
しかし、アフリカのザンビアで臨んだ農業研修で心が打ち砕かれました。現地は機械化が進んでおらず、人々は鍬で農作業をしていました。後進国の人はイメージと違って、すごく屈強で力強い。私は手伝うこともできず、ただ立ち尽くしていました。「私は教えられることはないし、何の役にも立てない」。無力感にうちひしがれて、後進国の食糧増産に携わる夢はあきらめました。
大学卒業後はイラスト広告の会社で働きましたが、交際していた大学の同級生が実家の農業を継ぐために石垣島に帰ることになり、その機会に結婚し、私も一緒に島で暮らすことになりました。2008年のことです。
彼の実家はハウスが46棟もある大規模農家でした。
結婚して早々に農作業の手伝いをする日々が始まり、1日10時間は働きました。我ながらすごく働いたと思いますが、中高生時代、ソフトボール部で培った体育会系の根性で乗り切りました。

一念発起! 有機農業を始める
石垣島で暮らしてから10年後、息子が喘息のアレルギーを起こしました。医師に話を聞いても原因はわからず、「完治はしません。薬で症状を抑えるしかない」言われました。息子がこれからもずっと苦しみ続けるのは親としては耐えられません。なぜ、アレルギーを起こしたのか。本を読んで調べるうちに食べ物が原因として浮かび上がりました。
アレルギーは免疫が外部から異物を排除するために発生しますが、腸内の免疫機能をコントロールするのは微生物です。微生物叢(びせいぶつそう)の豊かな土壌では、微生物が野菜にミネラルや窒素を供給し、健康でおいしい野菜が育ちます。
微生物の豊かな畑にするには、農薬や化学肥料を使う慣行農業ではなく、植物残渣(ざんさ)などの有機物で作物を育てる有機農法にする必要があります。有機農業は育成に手間がかかりますし、確実な収穫も見込めません。それでも自分の子供はもちろん、健康に悩む人々のことを考えるとやる価値はあります。大きな決断でしたが、夫に相談し、2人で有機農業をはじめると決めました。ただ、夫は市議会議員選挙に立候補する予定もあり、自分が中心に進めることになりました。
コツコツと販路を広げる
合成肥料からススキやカヤ、キビガラなど炭素率の高い資材に変え、害虫予防の農薬もやめました。ミネラル分の多い食物には虫が苦手で寄り付きません。有機農法に切り替えて最初の2年は作物が黄色くなり育ちませんでしたが、3年目には丈夫な野菜を収穫できるようになりました。そこからは慣行農業をやめて全面的に有機農業に切り替えました。
現在は、ズッキーニ、ナーバラ(へちま)、ミニトマト、にんにく、じゃがいも、ニンジン、タマネギと多品種の野菜を育てています。有機野菜で規格をそろえることができず、JAに出荷するのは難しいので、飲食店や消費者の方に直接販売をしなくてはなりませんが、当時(7年前)、石垣市では有機野菜の認知度が低く需要がほとんどありませんでした。知り合いに買ってもらったり、インスタグラムで発信したり、コツコツ活動することで、少しずつお客さんを増やしていきました。化学肥料を使った野菜よりも、とても甘くておいしいと喜ばれると、「やってよかった」という気持ちになります。



現在は5千坪のうちハウス2棟分+路地で10アールくらいの畑をひとりで切り盛りしています。忙しくて大変ですが、やりがいを感じています。将来的には畑全面で有機野菜を育てることを目指しています。

八重山ローカル認証制度「コラコラ」を立ち上げ
子どものアレルギーがきっかけで、有機農業を始めましたが、だんだんと島の環境にも意識が向くようになりました。子供たちが大人になったときのために美しい島も残しておきたい。そう思うようになった理由は海の変化です。石垣島のある八重山諸島は世界有数のサンゴ礁が生育していますが、近年は急激に死滅が進んでいます。海水温の上昇も原因ですが、陸地からの生活排水による富栄養化や沖縄特有の赤土の流出も影響を与えていると言われます。
見識を広げるため環境に関するイベントにも参加するようになり、その中で、地域でつくるローカル認証制度の存在を知りました。名前の通り、地域で環境負荷を軽減するためにガイドラインを作り、それを順守する人を認証するものです。調べると、環境負荷の軽減を目指した団体は各地にありました。
私は有機農業を通して豊かな土壌や自然環境を守りたいと思っています。認証制度によって同じような価値観をもつ職業の人たちが協働することで島の内外の人たちのサンゴ礁保全への意識が高まるような取り組みができたらと考えました。
そして2019年5月、数人の仲間と呼びかけ人になって、環境保全に興味のある友人らと八重山ローカル認証制度「コラコラ」を立ち上げました。サンゴ礁のcoralと協働のcollabolationの頭文字を組み合わせた名前です。
認証を受けられる条件は、農業の場合、
①使わない
②環境を考える
③生き物を考える
の3つの分野で、それぞれ3項目の達成基準があります。「使わない」では除草剤・農薬・化学肥料を使用しない、「環境を考える」では排水溝掃除の実施、自然に還る資材の使用、グリーンベルトの構築、「生き物を考える」では土づくりの実践、生き物の名前がわかる、畑に棒が1メートル以上刺さること(化学肥料やたい肥を使用する畑は硬盤層ができ深くまで刺さらないため)、で1分野につき1項目の取り組みが達成できていれば事務局から事業者に認証書が与えられます。事業者と消費者双方の意見を取り入れ、難しい数値目標ではなく、簡単に挑戦できる内容にしました。
私が所属する「花谷農園」は除草剤、農薬、化学肥料を使わず、排水溝を掃除し、自然に還る資材を使うことで環境を考え、土づくりを通して生き物を考えていますので、7項目をクリアし、認証を受けました。
「コラコラ」は第三者機関に担保させる一般的な認証制度と違って、ガイドラインを達成しているかどうかは自己申告にしています。多くの人の目に触れ、多くの人に関わってもらいたいので、あえて「ゆるさ」を優先しています。

環境への思いを共有するツアー
私たちは慣行農業や生活排水を一概に否定する気持ちはありませんし、何かを達成する目的や数値目標もありません。今は環境に優しい取り組みをしている事業者と自然に関心のある消費者がつながる流れを作るという思いを軸に活動しています。
現在は、趣旨に賛同してくださった飲食店や宿泊施設、小売店のオーナー27事業者が参加し、年8回勉強会を開き、食や環境保全について意見を交換しています。今年は県の事業である「島まーるツアー」にコーディネーターとして参加させていただきました。「島まーる」は、島とゆいまーる(助け合いを意味する沖縄の方言)を重ねた言葉で、沖縄本島と離島の住民が助け合っていこうという趣旨の事業です。
沖縄本島からの参加者が認証事業者の飲食店で食事をしたり、農家のお手伝いをしたり、赤土の流出を防ぐために裸地に芝を植えたりしました。陸域から海域の環境保全を考える視点は日本のどこに住んでいても必要だと思っています。多くの皆様にお伝えできるよう今後はツアーを充実させていきたいと考えています。
石垣島で暮らして17年。素晴らしいと感じるのは自然だけではありません。
近所の人が困っていたら、助けるのが当たり前。お金よりも時間を大切にする。人が生きるために大切なことが、島の人には備わっています。そんな人たちとともに未来の子どもたちのために美しい島をつないでいきたいと願っています。
花谷さんの石垣島イチオシ!
バンナ公園
県営の森林公園で広さ約400ha。海の見える展望台、熱帯植物園やアスレチックがある島民の憩いの場。花谷さんは子どもとよく遊びに行くそう。写真は「ふれあい子供広場」の芝生でくつろぐ花谷さん。


花谷まゆ(はなたに・まゆ)
1982年、石川県生まれ。2005年東京農業大学国際食糧情報学部卒業。08年結婚を機に石垣市で農業を始める。17年子供のぜんそくがきっかけで農薬を使う慣行農業から有機農業(炭素循環農法)に切り替える。21年さんごにやさしい八重山ローカル認証コラコラを開始。
1982年、石川県生まれ。2005年東京農業大学国際食糧情報学部卒業。08年結婚を機に石垣市で農業を始める。17年子供のぜんそくがきっかけで農薬を使う慣行農業から有機農業(炭素循環農法)に切り替える。21年さんごにやさしい八重山ローカル認証コラコラを開始。